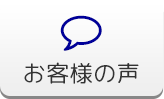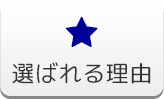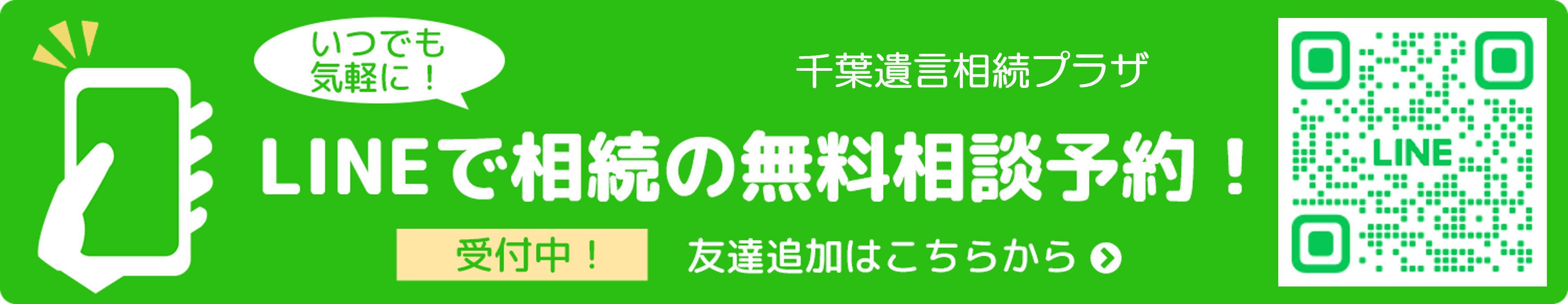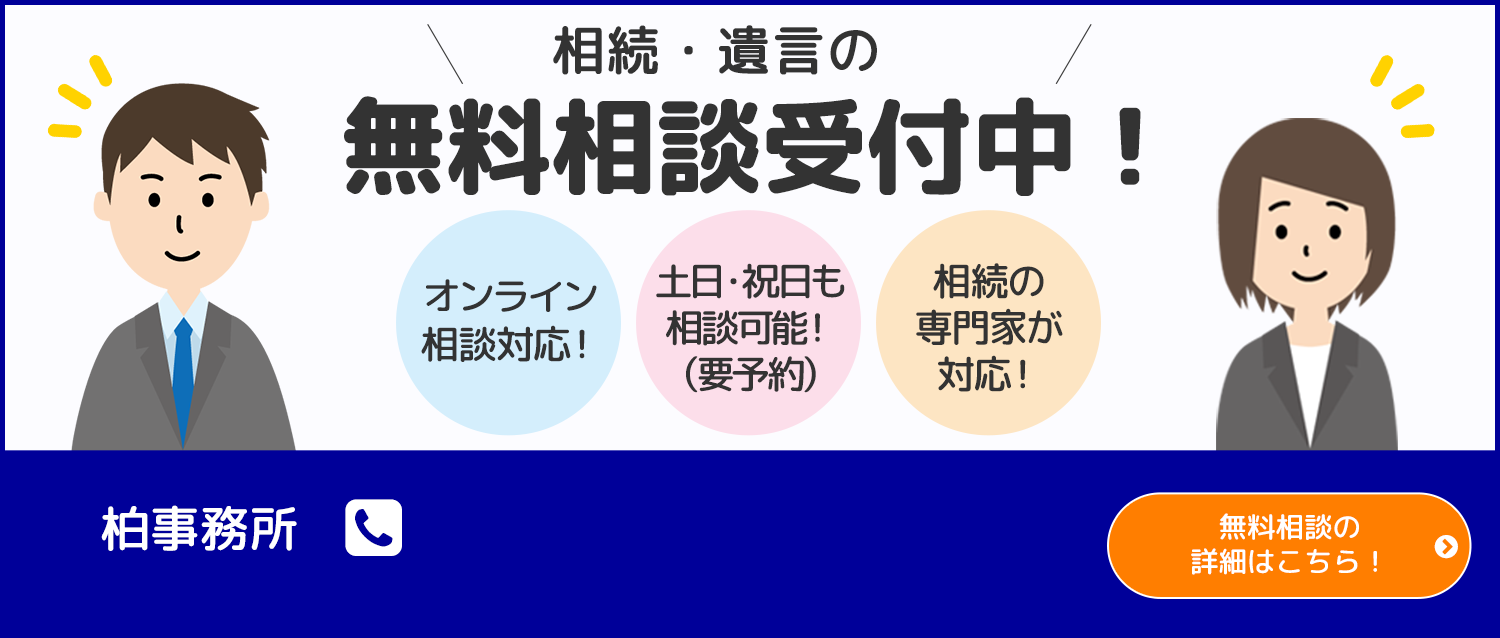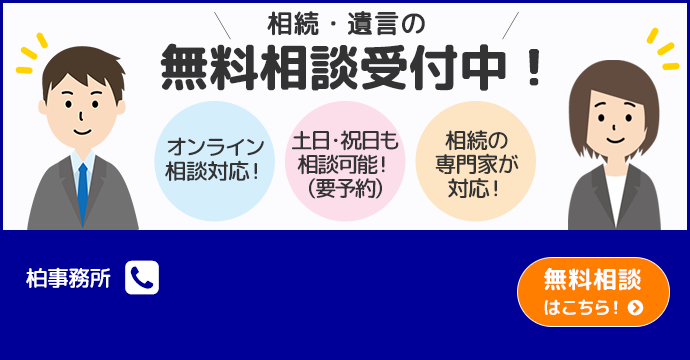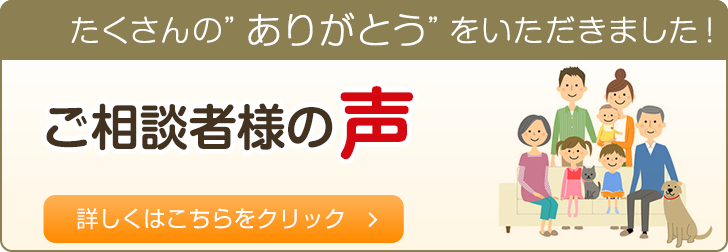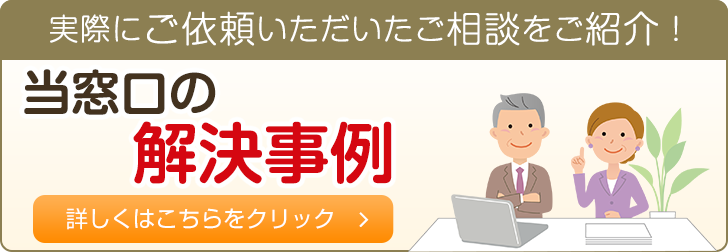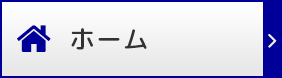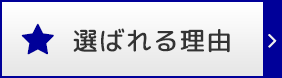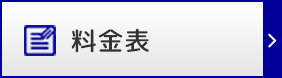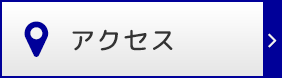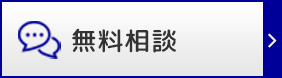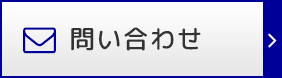相続財産の分割をスムーズに!代償分割のメリット・デメリットと手続きを徹底解説
 相続が発生すると、相続財産をどのように分けるかという問題に直面します。
相続が発生すると、相続財産をどのように分けるかという問題に直面します。
相続財産には、不動産、預貯金、株式など様々なものがあり、相続人全員が納得する形で分割することは容易ではありません。
特に、不動産のように分割しにくい相続財産がある場合、相続人間でトラブルに発展することも少なくありません。
そこで、今回は相続財産の分割の方法の一つである「代償分割」について詳しく解説していきます。
代償分割とは、分割しにくい相続財産を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人に対して金銭その他の財産で補償する分割方法です。
相続財産の分割で悩んでいる方、不動産などの分割しにくい相続財産をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
代償分割とは?
相続財産の分け方には、大きく分けて「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つの方法があります。
現物分割: 相続財産をそのままの形で各相続人に分割する方法
換価分割: 相続財産を売却し、その代金を各相続人に分割する方法
代償分割: 特定の相続人が相続財産を取得し、他の相続人に対して代償金を支払う方法
代償分割は、主に不動産のように分割しにくい相続財産を分割する場合に用いられる方法です。
代償分割の定義と仕組みを分かりやすく解説
代償分割とは、相続人の一人が相続財産を単独で相続する代わりに、他の相続人に対してその相続分の相当額を金銭またはその他の財産で支払うことで、相続財産の分割を行う方法です。
例えば、相続財産に不動産があり、兄弟2人で相続する場合を考えてみましょう。
兄が不動産を相続し、弟にその不動産の評価額の半分を代償金として支払う、あるいは兄が所有する別の不動産を弟に渡すことで相続財産の分割を行うことができます。
代償分割のメリット・デメリット
代償分割には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
相続財産を分割せずに済む: 不動産などを分割する必要がないため、共有状態によるトラブルを回避できます。
相続手続きがスムーズになる: 遺産分割協議がまとまりやすくなり、相続手続きをスムーズに進めることができます。
相続人のニーズに合わせた分割が可能: 各相続人の事情に合わせて、柔軟な相続財産の分割を行うことができます。
相続税の負担を軽減できる可能性がある: 特定の相続人が不動産を取得し、要件を満たせば「小規模宅地等の特例」の適用を受けやすくなるなど、相続税の節税効果が期待できる場合があります。
デメリット
代償金の支払いが発生する: 代償金を支払う相続人は、多額の資金が必要になる場合があります。
贈与税が発生する可能性がある: 代償金の支払いが、税法上贈与とみなされる場合があります。
相続人間で不公平感が生じる可能性がある: 代償金の評価額によっては、相続人間で不公平感が生じる可能性があります。
代償金の算出でトラブルになる可能性がある: 不動産などの評価方法によって代償金の金額が変わってくるため、相続人同士で意見が対立する可能性があります。
代償分割が向いているケース
代償分割は、以下のようなケースに向いています。
分割しにくい相続財産がある場合: 不動産や事業用資産など、分割しにくい相続財産がある場合
相続人の一人が相続財産を承継したい場合: 例えば、家業を継ぐために、一人が事業用資産を相続したい場合
相続人が遠方に住んでいる場合: 相続人が遠方に住んでおり、相続財産の管理が難しい場合
不動産を売却したくない場合: 例えば、被相続人が住んでいた家に住み続けたい場合
代償分割と他の分割方法との違い
遺産分割協議
代償分割は、他の相続財産の分け方と同様に、遺産分割協議によって行われます。
遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分割方法について話し合い、合意することです。
現物分割
現物分割と代償分割の違いは、相続財産を分割するか、代償金を支払うかという点です。
現物分割では、相続財産をそのままの形で各相続人に分割します。
一方、代償分割では、相続財産を分割せずに、代償金を支払うことで相続財産の分割を行います。
換価分割
換価分割では、相続財産を売却し、その代金を相続人で分割します。
代償分割では、相続財産を売却せずに、特定の相続人が取得します。
換価分割では、相続税以外に譲渡所得税が発生する可能性があります。
代償分割の手続き
代償分割を行うには、以下の手続きが必要です。
代償分割に必要な書類
代償分割では下記の書類を利用する場合が多いです。
代償分割に必要な書類は状況によって異なるため、相続の専門家へ相談し、用意をすることがおすすめです。
遺産分割協議書: 相続人全員の署名と実印が必要
相続関係説明図: 相続人全員の関係を図示したもの
戸籍謄本: 被相続人及び相続人全員の戸籍謄本
固定資産税評価証明書: 不動産を代償分割する場合
株式の株主名簿: 株式を代償分割する場合
不動産の評価に関する書類: 不動産鑑定評価書、路線価図など
具体的な手続きの流れ
遺産分割協議: 相続人全員で遺産分割協議を行い、代償分割について合意する
遺産分割協議では、誰がどの相続財産を取得するか、代償金の金額や支払方法などを決定します。
-
- 代償分割を行う場合は、他の相続人全員の同意を得ることが必要です。
遺産分割協議書の作成: 遺産分割協議の内容を記載した遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書には、分割方法、代償金の額、支払い条件、支払期日など、相続財産の分割に関する全ての詳細を記載します。
-
- 代償金を分割で支払う場合は、「代償分割によって代償金を分割払いする」といった一文と、1回あたりの支払額や分割回数なども記載します。
記載内容に問題がなければ、相続人全員で署名・押印をすることが必要です。
代償金の支払い: 代償金を支払う相続人は、他の相続人に対して代償金を支払う
名義変更: 代償分割によって相続財産を取得した相続人は、必要に応じて名義変更手続きを行う
不動産を取得した場合は、不動産登記の申請が必要です。
預貯金を取得した場合は、金融機関に名義変更の手続きが必要です。
株式を取得した場合は、証券会社に名義変更の手続きが必要です。
代償分割における注意点
代償分割を行う際の基本的な手続きと注意点は以下の通りです。
各手続きの具体的な流れや必要書類は、相続財産の内容や相続人の状況によって異なる場合があるため、相続の専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることもおすすめです。
代償金の評価
代償金は、相続財産の評価額を基に算定されます。
評価では評価額が適正かどうかを確認することが重要です。
相続財産の評価方法には「時価」「相続税路線価」「固定資産税評価額」などがあります。
評価方法によって代償金の金額が大きく変わる可能性があるため、相続人間でトラブルにならないように注意が必要です。
贈与税
代償金の支払いが、税法上贈与とみなされる場合があります。
そのため、贈与税の課税対象となる可能性があることを理解しておきましょう。
遺産分割協議書に代償分割であることを明記しておくことで、贈与税のリスクを回避できる可能性もあります。
所得税
現金ではなく不動産などの資産で代償を行う場合は、譲渡所得税が発生する可能性があります。
相続人間の合意
代償分割は、相続人全員の合意が必要です。
合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで相続手続を進める必要があります。
代償分割と税金
代償分割を行う際には、税金についても考慮する必要があります。
代償分割における相続税
代償分割によって相続財産を取得した相続人は、取得した相続財産の価額に応じて相続税を支払う必要があります。
代償分割の場合、相続税の課税価格は、以下のようになります。
代償金を支払った相続人:
課税価格 = 相続税評価額 ― 代償金額 × (相続税評価額 ÷ 代償分割時の時価)
代償金を受け取った相続人:
課税価格 = 相続税評価額 + 代償金額 × (相続税評価額 ÷ 代償分割時の時価)
例えば、兄が相続税評価額4,000万円、時価5,000万円の不動産を相続し、弟に代償金2,000万円を支払うケースでは、兄は2,400万円、弟は1,600万円をそれぞれの課税価格として相続税を支払います。
代償分割における贈与税
代償金の支払いが、税法上贈与とみなされる場合があります。
これは、代償金の額が、相続財産の評価額よりも著しく低い場合などに起こりえます。
例えば、兄が時価5,000万円の不動産を相続し、弟に支払うべき代償金が1,000万円だった場合、その差額は兄から弟への贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
代償分割と税金に関する注意点
専門家への相談: 代償分割を行う際には、相続の専門家に相談し、相続税や贈与税について適切なアドバイスを受けることが重要です。
税務申告: 相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
遺産分割協議書への記載: 代償分割によって代償金を受け取る際には、必ず遺産分割協議書に「代償金として○○に△△までに××万円を支払う」と明記しましょう。
上記は、代償分割を行う際の税金に関する基本的な注意点です。
具体的な手続きや必要書類は相続財産の内容や相続人の状況によって異なる場合があります。
代償分割の事例
代償分割は、様々なケースで活用できます。
具体的な事例をいくつかご紹介します。
不動産を代償分割する場合
相続財産に、自宅や賃貸マンションなどの不動産が含まれている場合、代償分割が有効です。
例えば、両親が亡くなり、兄弟2人で相続する場合を考えてみましょう。
兄が自宅を相続し、弟に自宅の評価額の半分を代償金として支払うことで、相続財産の分割を行うことができます。
この場合、代償金の金額は、自宅の評価額を基に算定されます。
不動産の評価方法には、時価、相続税路線価、固定資産税評価額など、様々な方法があります。
評価方法によって代償金の金額が大きく変わる可能性があるため、相続人間でトラブルにならないように注意が必要です。
株式を代償分割する場合
未上場会社の株式を代償分割する場合、株式の評価額を算定することが重要になります。
株式の評価額は、会社の業績や資産状況などを考慮して算定されます。
例えば、父親が経営していた会社の株式を長男が相続し、次男に株式の評価額の半分を代償金として支払うことで、相続財産の分割を行うことができます。
代償分割を行う際には、税金についても考慮する必要があります。
代償分割によって相続財産を取得した相続人は、取得した相続財産の価額に応じて相続税を支払う必要があります。
また、代償金の支払いが税法上贈与とみなされる場合があり、贈与税が課税される可能性があります。
代償分割に関するよくある質問
Q. 代償金の額はどのように決めるのですか?
A. 代償金の額は、遺産分割協議で相続人全員が合意する必要があり、一般的には、相続財産の評価額を基に算定されます。
遺産分割協議で解決する場合、相続人全員が納得すれば代償金を厳密に計算する必要はありません。
原則的な方法で算出した価額以外の金額を代償金とすることも可能です。
Q. 代償分割を行う際に、注意すべき点はありますか?
A. 代償金の評価額が適正かどうか、贈与税が発生する可能性がないかなどを確認する必要があります。
代償分割を行う際には、対象となる不動産の評価が必要です。
しかし不動産の評価方法は一律ではありません。
代償金を支払う相続人は低く見積もるでしょうし、受け取る相続人は高く見積もるでしょう。
したがって、意見が合わずにトラブルになってしまうケースも少なくありません。
また、代償金の額が相続財産の評価額よりも著しく低い場合や遺産分割協議書に代償分割の旨を記載していない場合には、贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
Q. 代償分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?
A. 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割協議で合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停でも解決しない場合は、家庭裁判所の審判によって解決することになります。
代償分割でスムーズな相続を実現しよう!
代償分割は、円満な相続財産の分割を行うための1つの手段です。
特に、不動産のように分割しにくい相続財産がある場合、代償分割によって相続人全員が納得する形で相続財産の分割を行うことができます。
代償分割を行う際には、メリット・デメリット、手続き、税金などを理解しておくことが重要です。
必要に応じて、相続の専門家に相談することをおすすめします。
今回のようなケースに当てはまる方は是非、一度当事務所の無料相談をご利用下さい!
柏相続窓口 ふらっとでは相続に関する無料相談を実施中!
当事務所では電話、LINE、メールでのお問い合わせを受け付けております。
電話は平日9:00~18:00の間にご連絡ください。
柏事務所:04-7170-1605
成田事務所:0120-054-489
四街道事務所:0120-222-612
メール、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております!